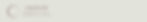top of page


美容師が着付けをできるメリット
顧客への提供価値の向上: トータルビューティーの提供: ヘアセットだけでなく、美容師が着付けも同時に提供できるようになるため、成人式、卒業式、結婚式、七五三、お祭りなど、着物が必要なイベントの際に顧客にとって一箇所で全てが完結する利便性を提供できます。 顧客単価の向上:...


「 コーリンベルト 」って和装なのにカタカナ?
コーリンベルトの名前は、この製品を開発した京都の会社「コーリン株式会社」の社名から来ています。


"おはしょり"って何のためにあるの?
女性の着物は身長より長いので、それを腰部分で折り返して帯の下に出して着ています。この部分がおはしょりです。


着付けの出来る美容師は需要が高い
「着付けは着付け師に」
「ヘアセットは美容室で」と分けることもできますが、利用者にとっても楽なのは『一気にすべてを終わらせること』
このような理由で、着付けの出来る美容師は需要が高いと言えます


コモチヅキの由来
小望月(こもちづき)・十四日月(じゅうよっかづき)。。。
満月の前夜の月で、「待宵の月(まつよいのつき)」ともいう。
翌日の満月を楽しみに待つ、という意味。
また、幾望(きぼう)とも言い、満月(望月)の前夜で、“機”は「近い」の意味を持つ。


十三参り
お祝い行事のトレンドは時代とともに変化し、七五三を3歳の男の子も祝うようになったり ハーフバースデーが欧米から日本に定着したりと 新しい文化が生まれています。


卒業式・入学式の“母きもの”
入学式や卒業式の主役は子どもなのだから、母親が着飾る必要はない。などと言う人もいるようですが、きちんとした姿で参加することは母としての礼儀。
お世話になった、もしくはこれからお世話になる先生方に、目に見える形でご挨拶をしている姿なのです。


袴(はかま)の種類
袴(はかま)は、日本の伝統的な衣装の一つで、主に和服に合わせて着用されます。袴は足を覆う長いスカート状の部分が特徴で、男女問わず着用されます。袴は伝統的な日本の美しさと実用性を兼ね備えた衣装です。
この袴の種類について説明します。


七五三で使用する小物の謂れ(いわれ)
七五三シーズン!
そんな七五三で使用する小物の謂れ(いわれ)を紹介します❁⃘*.゚
小さな小物にも、一つ一つ想いが込められており 調べれば調べるほど面白いですよ!


早生まれの子の七五三はいつ祝う?
七五三のお参りは、本来は数え年で行うものとされている地域が多いようですが、満年齢、数え年 どちらでお参りしても問題ありません!
3歳のお参りだと、着物が大きすぎたり、落ち着きがなかったり、、
色々と心配な事もありますが、それぞれのご家庭にあった時期にお参りすると良いですね◎


お太鼓の歴史は浅かった
お太鼓の歴史は浅かった?!
お太鼓結びは和服の帯結びの基本!
というイメージを持たれがちですが、実はそれほど歴史の古い結び方ではありません


夏のお宮参りも 着物がいい
夏のお宮参りも 着物がいい
ひとつひとつは手軽に出来ることなのでしっかり暑さ対策をして、夏でも着物のおしゃれを楽しみましょう


浴衣で行けるところ、行けないところ
「どこに着ていくのが正解なの?」
「逆にダメな場所はあるの?」
こんな疑問も あるでしょう𓏸︎︎︎︎𓈒 𓂃☁️𓂃 𓈒𓏸


アイテム別お手入れ方法
小物編です👌🏻 ̖́-
着物と同様に小物もできれば長く綺麗な状態で保ちたいですよね!
是非セルフメンテナンスの参考にしてみて下さい😊


なぜ卒業式に袴(はかま)を着るの?
今までの学問を終え、また新しい始まりを迎えるための卒業式。
人生に一度のビッグイベントですよね!そんな卒業式といえば、卒業袴!!
今回は 袴 についての小話を(°-° 👂)


帯締めアレンジで可愛さ増
帯締めは 帯を固定するための「着付け小物」ですが、着物のコーディネートを彩る「装飾品」としての楽しみもあります😙⋈


振袖美人のつくりかた
美しい衣装、振袖👘
日本の伝統美を凝縮したようなうっとりする振袖は 成人式の華というべき存在ですよね!
着物もメイクも髪型も完璧💄🪞✨
そんなあなたに必要なものは何でしょうか?


成人式で振袖を着る意味とは?!
成人式には、振袖を身につけるのが日本ならではの文化となっていますよね。当たり前のように行われている成人式!他の国にはない文化で、民族衣装である着物を着て行なわれる行事なので、世界的にも評価されているのです。


「着物1枚に帯3本」とは?
皆さん、着物を選ぶ時どのように選んでいますか?!結婚式にはこの着物とこの帯のセット、七五三はこのセット! 着物と帯のコーディネートを決めている!という方、多いと思います。


帯の歴史
帯の歴史は、前開きの服を着るようになり、衣服の前が開かないように腰に巻いたことからスタート
bottom of page